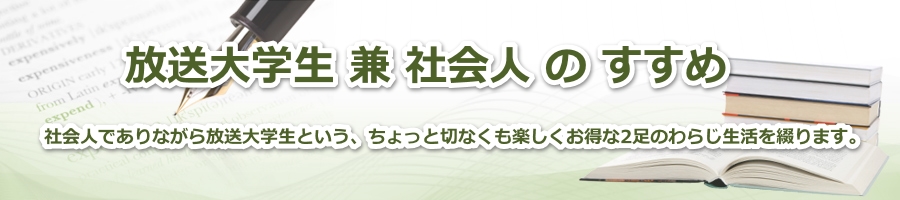放送大学生兼社会人のすすめ
放送大学生兼社会人のすすめご質問等あればお気軽にどうぞ!
特典付きの無料メルマガ登録
ツイート
【放送大学エキスパート資格】学校地域連携コーディネーターの特徴と難易度分析
放送大学エキスパート資格(認証状)の学校地域連携コーディネーター(学校地域連携コーディネータープラン)の特徴と科目別難易度ランキング分析をご紹介します。

学校地域連携コーディネーター(学校地域連携コーディネータープラン)の特徴
学校と地域の連携や協働を促進するには、どんな知識やスキルが必要かご存知ですか?放送大学の学校地域連携コーディネータープランでは、学校や地域の特性や課題、ボランティアの管理や支援、子どもの発達や心理など、幅広く学ぶことができます。このプランを修了すると、コミュニティ・スクールや地域学校協働本部などの取り組みにおいて、学校と地域のつなぎ役となるコーディネーターの資格を得ることができます。学校地域連携コーディネータープランは、学校と地域の協力を深めたいという方におすすめのプランです。 ※「学校地域連携コーディネーター」は、放送大学だけの呼び名です。
今後公立小中学校に置かれることが期待されている「地域コーディネーター」、学校側の窓口として地域連携の企画・調整等を行うことが想定されている「地域連携担当の教職員」、社会教育主事、学芸員、司書などの生涯学習に関わる職員、また、学校を含む地域活動を実践するNPOの者、NPO中間支援組織の職員などによる認証取得が望まれます。
・社会教育主事とは、都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に置かれる専門的職員で社会教育を行う者に対する専門的技術的な助言・指導に当たる役割を担います。また、社会教育主事補は、社会教育主事の職務を補助する役割を担います。
・学芸員とは、「博物館法」に定められた博物館(美術館・ 天文台・科学館・動物園・水族館・植物園なども含む)に置かれる専門的職員のことで、国家資格です。博物館で働きたい方は必要な資格です。
・司書とは、図書館において、資料の選定から貸出、読書案内に至るまでの全般的な業務を行う専門職です。司書補は司書の補助的役割を担います。どちらも図書館法による国家資格です。
学校と地域の架け橋となりたい人の役に立ちたい方におすすめです。
学校地域連携コーディネーター(学校地域連携コーディネータープラン)の認証取得条件
授業科目群55単位の中から、必修科目6単位、選択必修2単位以上を含めて、14単位以上を修得すること。
認証状取得に相性の良いコースは、心理と教育コース、社会と産業コースであり、生活と福祉コース、人間と文化コース、情報コース、自然と環境コースとも関連性があります。